今回は本場アメリカのバス釣りトーナメント団体Major League Fishing メジャーリーグフィッシング(以下MLF)ついて詳しく調べてみました。
MLFはアメリカのバス釣り競技団体で、他組織のB.A.S.S.と人気や規模を2分する団体です。比較的最近発足した組織で、たくさんの独自の特徴を持っています。
そもそもアメリカのバスフィッシングは、子どもも大人も楽しめるアクティビティとして普及しています。また他の側面として、プロスポーツとして浸透していたり(地域によりますが)、エンタメとして人気があったり、市場規模も大きく一大産業となっております。
MLFは歴史と伝統のあるB.A.S.S.と違い、後発なことを武器として色々な革新的なことに挑戦している団体です。
日本のバス釣り団体BMCとパートナーシップを結び、「MLF Japan Kasumi Series」が発足したことも話題となりました。
以下にいくつかMLFの特徴をまとめてみました。
テレビ番組としてのおもしろさの追求
そもそもMLFという組織は、アメリカの有料TVチャンネルの「アウトドアチャンネル」とのパートナーシップの間で設立されました。
そのためMLFは、トーナメント(大会)をTV放送前提に運営しています(近年はネット配信)
視聴率を獲得するためにトーナメントの「見せ方」にもこだわっていて、釣り好きのための専門番組でなく、誰もが楽しめるエンタメスポーツ番組を目指しています。
個人的には日本でいうプロ野球のようにコアなファンだけでなく、「TVをつけてやっていたら見る」という一般層をターゲットとしている側面と、エンタメとして好きなドラマやバラエティ番組・アニメなどを「楽しみに待って見る」という側面を両方兼ね備えた番組を目指していると解釈しています。
MLFが視聴率を気にするのには理由があって、団体を発足し成長させるために、釣り業界以外からもスポンサーを集める必要があり、TVの視聴率、つまり人気が出るかが重要になってきます。人気が出なくて利益が出なければ、他業界からのスポンサーが撤退してしまい組織運営の存続にも関わります。
設立時は釣り業界以外から、ゼネラルタイヤ(アメリカのタイヤメーカー)やシグ・ザウエル(アメリカの銃器メーカー)・ガイコ(アメリカの自動車保険会社)などスポンサーになりました。
また近年は視聴率向上のために(結果的に見る人を楽しませるため)、MLFの大会の中でも最もレベルの高いバスプロツアー(以下BPT)で改革が行われています。
それは出場選手を減らし一人ひとりにスポットライトが当たるようにすることです(2024年は80名、2025年は65名、2026年は50名)
人数を減らして視聴者に選手の名前と顔を覚えてもらい、釣りの成績だけでなく選手のプライベートやアイデンティにも着目し、視聴者が感情移入しやすくして、共感を得やすくする方針です。
公式ホームページを見ても、出身地や趣味はもちろん家族構成も掲載されています。(家族構成といっても家族の名前だけでなく、結婚していないガールフレンドの名前まで掲載されています!)
確かに日本の格闘ゲームでも以前は、キャラクターの名前や出身国・使用する拳法など簡単なプロフィールしか決まっていませんでしたが、徐々にそのキャラクターの生い立ちや、趣味や好きな食べ物・身長体重など現実の人間と変わらないような設定が事細かに決められるようになり、それによってプレーヤーに感情移入しやすくしたり、興味を持ってもらうことで人気が出たというケースに似ていると思います。
独特の試合ルール
そもそもバス釣りトーナメントは、湖や河川をバスボートというバス釣りのためだけに開発された専用の船に乗って釣りをして、釣ったバスの総重量で競うというルールが一般的です。また計測できる魚の大きさ(重さ)が決まっていて(キーパーサイズ)、計測できる魚の数なども制限されているトーナメントが多いです(プロの大会は5匹制限が多い)
また自分の釣ったバスはボートに搭載されているライブウェルという専用生簀に入れて、計測場所へ持っていき、審判に重量測定を依頼するという流れが一般的です。
しかしMLFは、全選手一人ひとりに、審判員がバスボートに同乗して、釣ったバスをその場で計測し、すぐにリリースされます(逃す)。バスを資源として考え、必要以上にダメージを与えないという考えで運営されています。また当然ながら審判員が計測するためそれは公式記録となり、TVを見ている視聴者にも各選手のスコアがわかるということです(そもそもどの競技でも、リアルタイムでのスコアがわかるのが当然で、最後までスコアがわからないシステムが異色とも言えますね)
またほとんどのバス釣りトーナメントは釣った魚の重い方から順に5匹を計測しますが、MLFは釣った魚の数は問われない運用です(最低重量はあります。また2023年は例外的に5匹の匹数制限があるルール運用)。つまり釣れば釣るほどスコアアップします。もちろんそれは戦術にも関係し、数は少なくても大型を釣る戦法や、サイズはそこそこでも数をとにかく釣るという作戦です(近年は※ライブサイトの影響で数を揃える戦略が優勝に絡むケースが多い)
また多様な戦術は当然TVを見ている人を楽しませることにも繋がります。
※ライブサイト・・・前方ライブソナーを用いた戦術。前方ライブソナーとは、リアルタイムで水中の情報がわかる画期的な魚群探知機のこと。ガーミンというメーカーの「ライブスコープ」という魚群探知機が有名です。
今までの魚群探知機というのは、船が通った真下の情報が瞬時にモニターに映し出されるという仕組み出した。それを高速で繋ぎ合わせたものが従来の魚群探知機です。
つまり過去の情報です。
一方でライブソナーとは簡単にいうと、水中ビデオカメラのようなもので船の前方の情報を現在のライブ映像としてモニターに映すことができます。つまり船が通過していない前方の情報をリアルタイムでモニターに映すことができます。
従来の魚群探知機では魚がモニターに見えてもそれは過去の映像のため、当然魚が動いていれば、もうそこにはいません。
しかし前方ライブソナーなら、魚が何m先の水深何mにいて、動いていようが止まっていようがモニターに映ります。肉眼では見えないが、モニター越しに「見える魚」を釣るという戦術がライブサイトです。
高額な賞金
現アメリカのバス釣りトーナメントでは最高クラスの賞金が用意されており、まさにアメリカンドリームを掴むことができます。トップクラスカテゴリーBPTのレギュラー戦の優勝賞金は15万ドル(約2,200万円)です。
優勝賞金が高いのはBPTだけでなく下位カテゴリーにも十分な賞金が用意されています。生涯賞金獲得額が億を超える選手もたくさんいます。
カテゴリーの豊富さ
バスプロツアー
MLFの中で1番ハイレベルなプロカテゴリーです。年7戦のステージツアー(ポイント制になっており、1位に1番多いポイントが与えられ、2位、3位・・・とだんだん付与されるポイントが減っていきます)と、その成績上位者のみが出ることができる最高峰の決戦レッドクエストという試合があります。年7戦の獲得ポイント合計1位に送られる年間王者・アングラーオブザイヤー(AOY)の称号とレッドクエスト戦の優勝が最も名誉ある称号と言えます(もちろんそれぞれに特別賞金があります)
また昨年度のシーズンの釣ったバスの平均重量の重い選手のみが出れるヘビーヒッターズというお祭り的な特別試合も用意されています(賞金あり)
インビテーショナルズ
タックルウェアハウス(アメリカの釣具屋通販サイト)を冠とするBPTの1つ下のプロカテゴリー。しかし優勝賞金も高額で、BPTから降格した選手や逆に期待の若手など実力者が揃うカテゴリーです。さらに好成績を残すと、BPTのレッドクエストにも出場できます。
トヨタシリーズ
インビテーショナルズのひとつ下のカテゴリー。プロカテゴリーの中では1番下位に位置するクラスです。ただエントリーフィー(大会参加費)は低いものの、賞金は決して低くはありません。たくさんの地域で大会が開かれるため、自宅の近くで参戦できるメリットもあります。また好成績を残すとトヨタシリーズチャンピオンシリーズに出場でき、そこでも好成績だとインヴィテーショナルズへ昇格できます。
フェニックス バスフィッシング リーグ
アメリカのバスボートメーカーのフェニックスを冠とするアマチュアリーグです。ウィークエンドアングラー、つまり週末だけ釣りをする社会人トーナメントとも言えるリーグ。アマチュアカテゴリーながらも賞金も用意されています。また試合も一日だけのワンデートーナメントとなっているという特徴もあります。また成績優秀者にはトヨタシリーズ参戦の機会も与えられます。
アブガルシア カレッジ フィッシング
釣具の総合メーカーのアブガルシアが冠のリーグ。アマチュアカテゴリーで大学生のリーグ戦。学生トーナメントながらも賞金も用意されています。スポーツDAYでは、プロと一緒に同じフィールドで釣りをすることもできます。また成績上位になれば、トヨタシリーズチャンピオンシップに進むこともできます。
アブガルシア ハイスクール フィッシング
アマチュアカテゴリーで高校生のトーナメントです。好成績を残すと、なんと奨学金も用意されています。アメリカとカナダの23,000以上の学校がエントリーしていて、放課後のクラブ活動のようなイメージです。またカレッジチームとコーチと繋がることもできます。
金儲けだけではない組織の姿勢
エンタメ性を高めて利益を上げようとすることはもちろんですが、MLFはそれだけではないと思います。公式ホームページを見てもそれがわかります。バスフィッシングがどれだけ素晴らしいアウトドアでのアクティビティかが記載されており、MLFを通してその素晴らしさを体感するきっかけになればいいとあります(若干筆者の解釈が入っています)
また先述したカテゴリーの多さもMLFのバス釣りに対する姿勢が伝わってくる運営だと思っております。
プロカテゴリーのBPT→インヴィテーショナルズ→トヨタシリーズ→アマチュアカテゴリーの社会人リーグ フォニックス→大学生のカレッジリーグ→高校生のハイスクールリーグとしっかりと段階分けされており、それぞれのカテゴリーで好成績を残せば上のクラスにステップアップできるシステムなど、バス釣りの未来(若手の育成)も見据えたこの運用は他に類を見ません。
またブラックバスを資源として捉え、環境保全にも力を入れている姿勢も見えます。それがデジタルウェイン方式にも表れているのではないでしょうか。末長くバスフィッシングを楽しめる環境を守ろうとしているのだと思います。
最終的には金儲け(企業の発展)に繋がっていくのかもしれませんが、こういったMLFの姿勢には共感しています。
BPTの注目選手
最後にMLF(BPT)を観戦するにあたり注目選手を紹介します
ジェイコブ・ウィーラー
誰もが認める最強アングラー。数年前から圧倒的強さを見せ、トーナメントのトップ10以内は当たり前、優勝も何回もしています。また年間優勝(AOY)も複数回に及びます。ライブサイトをアメリカで最も早く取り入れ、戦術として昇華させて多くの好成績に絡んできました。もちろんライブサイトだけでなく、シャローフィッシングやカバーフィンシングも得意で釣り方に資格無し。まさに現役最強トーナメンターです。
なお何度も年間王者になったり、ライブサイトという得意技を武器に戦う姿は、同じくレッグワームやモコリークローという得意技を駆使して戦う日本の最強トーナメンターの小森 嗣彦選手に重なるところがあると思っています。MLFと日本のBMCがパートナーシップを結んだため、いつかウィーラー選手と小森選手が同じ舞台で戦う日が来るのを、期待せずにはいられません!なおウィーラーは小森選手のような大ベテランではなく中堅アングラーの年齢です(ウィーラー選手も筆者の年上だと思っていましたが年下でした w)
ダスティン・コネル
ウィーラーと並ぶ最強トーナメンターの一人で、ウィーラーとも親交が熱い。同じくライブサイトを中心とした、バーサタイルアングラーで死角がない釣りを展開します。特徴としてはレッドクエストなどの大舞台に強く、賞金額だとウィーラーを上回るときもあります。
ドリュー・ギル
2024年にBPTにデビューした新星ドリュー・ギル。若干22歳(2025年8月時点)の年齢ながらも圧倒的なライブサイト技術で、あっという間にBPTを席巻しました。年間優勝も射程圏内に収める超期待の新星です。
キース・ポシェ
筆者が個人的に注目している選手がキース・ポシェです。ライブサイト戦術が一般的になったトーナメントにおいて、従来通りのシャローを中心とした釣り方を得意としています。また釣り方だけでなく、キース・ポシェを注目している理由は他にもあります。それはポシェの戦い方です。2023年はB.A.S.S.とのダブル参戦をし、B.A.S.S.のファンサービスをすっぽかしてB.A.S.S.に怒られたり(ファンを大事にしていない訳でなく、日程の関係でやむなく)、大型ボートが主流のアメリカプロツアーにおいて、小型のアルミボートで戦う姿にファンの共感を得ています。というのも、もちろん大型ボートは維持費やガソリン代も多くかかり、一般のアングラーには手の出せないものになっています。そんな中、コスト面も安いアルミボートで戦うポシェの姿は、近年の物価高騰でフラストレーションの溜まったアメリカ人に支持される理由となっています。
もちろん無理に反抗したわけではないと思いますが、B.A.S.S.などの大型組織(権力・上司とも言える)を恐れない姿や、近年のアメリカ社会の状況を快く思っていないファン層の獲得は、アメリカのプロレス団体WWF(現在はWWE)に所属していた、ストーン・コールド・スティーブ・オースチンが日々の生活に鬱憤の溜まった人々の発散の象徴として、権力・上司に刃向かい、リング上でビールを飲みまくるパフォーマンスなどで人気が出たこととも共通する部分があるのではないかと思っています。
大森 貴洋
言わずと知れた日本の雄ベテラン大森選手。ライブサイトではなく、昔ながらのシャローを中心とした立ち回りは、持ち味をしっかりと発揮していると言えます。ライブソナーの使用に時間制限が設けられた今後のシリーズではぜひ優勝を狙ってもらいたいと思っています!
以上アメリカのバス釣り団体のMLFについて調べてみました。
(Wikiや公式HPをもとにしていますが、バス釣り雑誌バサーの雨貝健太郎さんの記事も参考にさせていただいております)
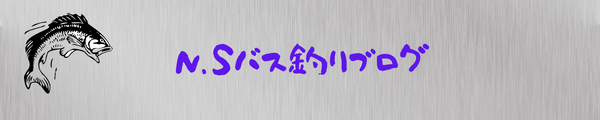
-について調べてみた.png)


コメント